はじめに
部下を持った瞬間から“リーダーシップの壁”は始まります。
「どう接すればいいのか分からない」「つい自分でやったほうが早いと抱え込んでしまう」──そんな悩みはありませんか?
私自身もまさにそうで、プレイヤーから責任者になった今、“無免許運転”のまま走っていたと気づかされました。
正直「人育てる免許なしで走ったら事故るに決まってるやん」と、自分にツッコミを入れました。
最初の衝撃「無免許運転」
冒頭の「リーダーなのに育成免許を持たずに走っている」という指摘に、いきなり心臓を撃ち抜かれました。
要は「無免許で高速道路に突っ込む」状態。
働いたら負けどころか、働いたうえに事故ってる。
マネジメントの再定義
「人を管理監督すること」ではなく、「人を介して仕事をする技術」。
“管理”って言葉には監視カメラ的な窮屈さがあるけど、“技術”ならRPGのスキルみたいに伸ばせる。
「スキルツリー埋めんかい」って自分に喝を入れたくなりました。
「自分でやったほうが早い」罠
最も耳が痛いところ。
実際に私も「はいはい、私がやります」と抱え込み、残業だけ増える日々。
結果、部下は育たず、自分は疲弊。
これぞ「最速で共倒れする黄金ルート」。
リードマネジメントとボスマネジメント
命令や監視で動かす「ボスマネジメント」は、まさに北風。
一瞬は力強くても、人はコートを握りしめ、心のシャッターを閉ざしてしまう。
私自身、いつも「ああはなりたくない」と思って生きてきました。
特に忘れられないのが「そう思わん?」という口癖。
あれは相手の同意を強制する言葉にしか聞こえず、心の中でいつも(思わん!!!)と返していました。
強制的に自分の思想を押し付ける態度が、本当に不愉快だった。
だからこそ私は、絶対に部下に使わないと決めています。
一方「リードマネジメント」は太陽のように信頼を育てる。
やっぱり自分はそっちを選びたい。
欲求とモチベーションの理解
マズローの欲求段階や「モチベーション2.0→3.0」の話は、他の書籍ともつながりがあり印象的。
外部刺激を「内発的動機」に変える。
テンションスイッチぐらい、自分で押すしかない。
心に残った言葉たち
- 「人は変えられない。でも人は変われる。」
- 「メンバー本人が自ら変わるために、マネージャーである私ができる習慣」
- 「相手のラインに期待値を合わせる」
どれも腹に刺さる。特に最後のは“勝手にハードル上げがちな上司あるある”を粉砕してくれました。
NG3パターンとあるある感
- ボスマネジメント
- 放任マネジメント
- 言うべきことが言えないマネジメント
この3つでほぼ網羅される。
つまりラスボスは「外の敵」じゃなく「自分のマネジメント癖」。
プライオリティマネジメントと行動の型
「第1象限を委任し、第2を拡張し、第3を減らし、第4をやめる」。
これは“時間管理マトリクス(緊急×重要の4象限)”を応用した考え方です。
本書がユニークなのは、それを「L字型行動からZ型行動へ」と整理しているところ。
理想は高いけれど、フレームがあることでゲーム感覚で挑めそうだと思えました。
感情の壁
結局のところ、知識や仕組みよりも手ごわいのは「自分の感情」。
イラっとした瞬間に冷静さが吹っ飛ぶ。
感情を横に置くだけでいい──そう言われても「置く場所どこやねん」と自分にツッコミを入れたくなります。
でも、これができるかどうかが分かれ道。
仕組みを憎んで人を憎まず
「問題の98%は仕組みの問題、人の問題は2%」。
「仕組みを憎んで人を憎まず」。
これは自分の信条とも重なり、胸にストンと落ちました。
まとめ
『部下をもったらいちばんに読む本』は、「人をどう動かすか」ではなく「人を介して成果を出す技術」としてのマネジメントを教えてくれる。
耳の痛い指摘も多かったけど、それをどう習慣に落とし込むかが自分の課題。
明日からはまず、「感情を横に置く」を小さく実践してみます。
今日も角砂糖ひとカケ🧊
仕組みを憎んで人を憎まず、感情を横に置き、背中で語る。
なで肩猫背ですわたくし。。。
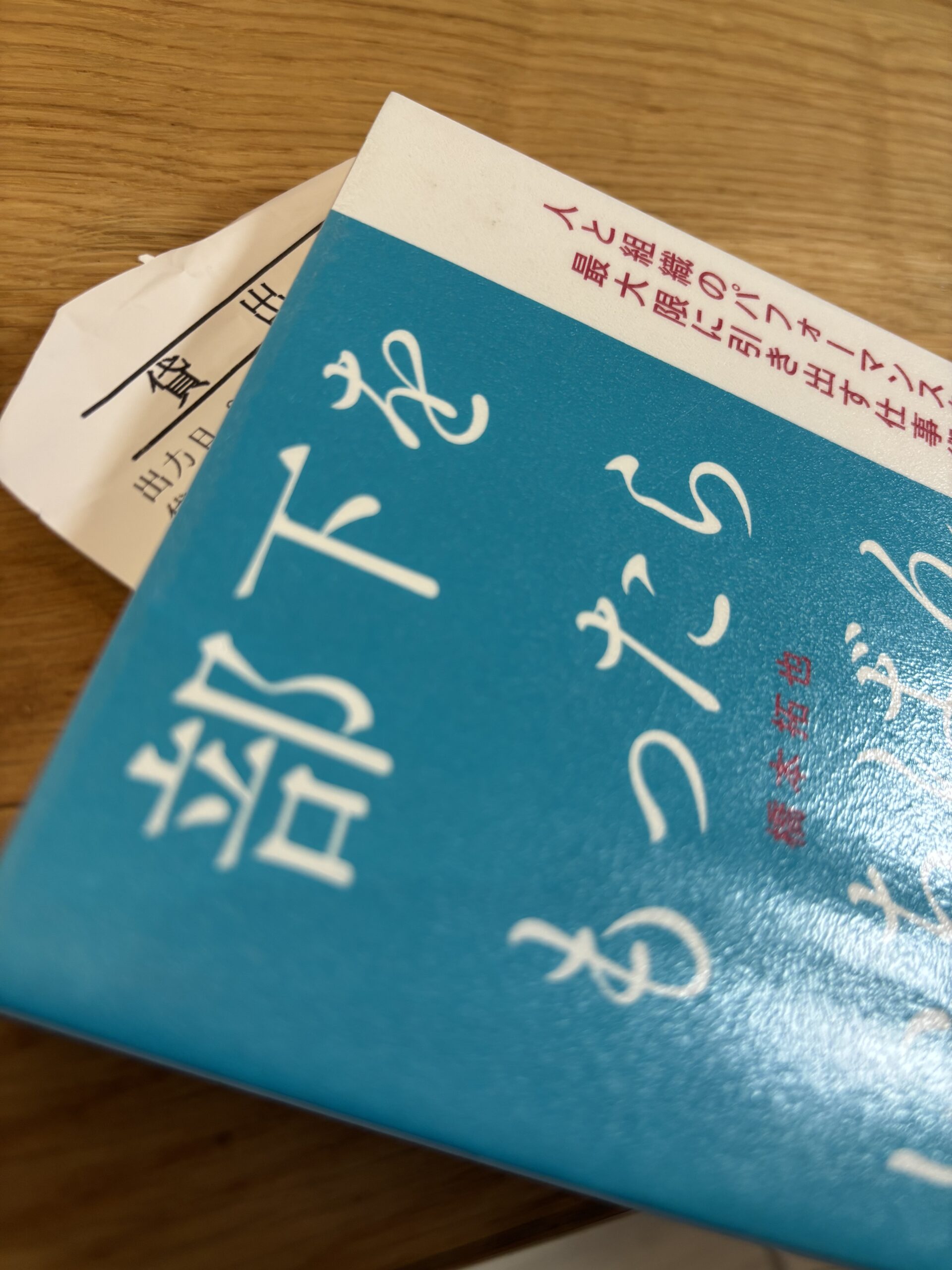
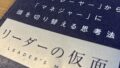

コメント